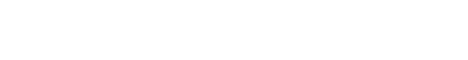TOPICS
- E-スポーツバイクと普通の電動アシスト自転車の違いって?
- テストで選んだ舞台は国道暗峠(くらがりとうげ)
- 暗闇の、暗峠ヒルクライムチャレンジ
- ヤマハのYPJ-TCの場合
- ルイガノのASCENT e-sportsの場合
- E-スポーツバイクは、普通の電動アシスト自転車とどれくらいアシスト力が違う?
- 電動アシスト自転車の限界
- 参考資料 道路構造令第20条
E-スポーツバイクと普通の電動アシスト自転車の違いって?
E-スポーツバイク(e-bike)って何やら楽しいらしいけど、ただスポーツ車に電動アシストユニットと大型のバッテリーを積んだだけで、アシスト力は変わらないんでしょ?と思う方も多いでしょう。
確かに、日本国内では「道路交通法」で電動アシスト自転車に関するルールが決まっていて、アシスト比は人が漕ぐ力「1」に対して電動アシストは最大「2」まででないと自転車としては認められません。
また時速24キロ以上ではアシストが“0”にならなくてはいけないルールがあります。
しかし、E-スポーツバイクの場合はスポーツ走行を行うことが大前提なので、モーターユニットに各社こだわりの味付けをしており、街中でよく見かけるシティサイクル型の電動アシスト自転車とは違った走行感になるのです。

国内で普及している、シティサイクルタイプの電動アシスト自転車。同じセンターユニットながら、フロントギアの後方に付いている小さなモータースプロケットに力を加える仕組みで、低速でのストップ&ゴーに強いが、ペダリングの際のダイレクト感は少ない。

E-スポーツバイクのユニット。(SHIMANO STEPS E8080)
踏み込みに対してのダイレクト感が特によい。重量物が中心の、さらに下にあることで、スポーツバイクならではのコントロール性能が損なわれていない。
テストで選んだ舞台は国道暗峠(くらがりとうげ)
選んだ舞台は大阪から奈良に抜ける国道(酷道)308。通称暗峠(くらがりとうげ)。
文句なしの激坂。
「暗がり」の名称の起源は、「椋ケ嶺峠」が訛って「暗がり」となったとする説から、樹木が鬱蒼と覆い繁り、昼間も暗い山越えの道であったこと、 また「鞍借り」、「鞍換へ」など諸説あります。
上方落語の枕では、「あまりに険しいので馬の鞍がひっくり返ることから、鞍返り峠と言われるようになった」と言うそうです。
ちなみに、暗峠の平均斜度は17%と言われており、最大では35-37%!スキー場の上級者コースか!!
以前、シティサイクル型の電動アシスト車でテストしたことがありますが、斜度17%位でかなりきつかった記憶があります。

人によると思いますが、これに10kg以上の荷物や、お子様を乗せたらまず登れないです。こぎ出すこともできないレベルです。

斜度最大部分。両立 スタンドをかけてもずるずる落ちてくるレベル。
今回は、背中にカメラ、三脚、充電器などもろもろ7-8kg位のバックパックを背負ってチャレンジです。
暗闇の、暗峠ヒルクライムチャレンジ
ほんとに国道?と疑いたくなりますがちゃんと一般国道です。

もう、序盤から容赦ない激坂です。街がこんなに近くに見えるのにこの高さ。

道路構造令第20条(※1)縦断勾配によると、道路の最大勾配は普通道路にあっては9%、小型道路にあっては12%と決められています。
※1 道路構造令第20条については、文末をご覧ください。
難しいことは置いておいて、国道なのに、平均17%の暗峠はまさに例外なのです。
さらに、こんな大きな溝も・・・。20インチ小径車にはダブルで酷です。
はっきり言って、自転車で走るべきではない所です。

今回はヤマハのYPJ-TC とルイガノのASCENT e-sports(アセント eスポーツ) 20インチ でテストしました。
果たしてシティサイクル型の電動アシスト自転車と比べてどうなのか?
ヤマハのYPJ-TCの場合
YPJ-TC のスペック
タイヤサイズ:700×35c
重量:22.3kg(S)、22.6kg(M,L)
変速:2×9(18段変速)
バッテリー容量:36.0v×13.3Ah

出発は弊社東大阪吉田店から。
この時のバッテリー残量は45%でした。

「なんだこれは・・・」
ハイモードで走れば、ここが平地と錯覚する程スムーズに走れます。だからと言って、エコで走れば、足を着くほどではないけれど、ちょっと強い運動負荷がかかるという感じです。

ライトを切ったら、周りが一切見えなくなる暗さですが、純正のライトの光量は十分で、不満は感じませんでした。
地面の凹凸もはっきり視認できました。
大阪側でのきつい所で約35-37%の急勾配がS字カーブになっており、タイヤの跡が散見されます。
なぜタイヤ跡がつくかについては、一言で自動車でさえ登る時にタイヤが空転してしまうほどの坂であることを意味します。

ちなみに、同じ山(生駒山)の奈良側を走るケーブルカーの斜度が約27%。

今度はこの一番きつい部分を走れるのか?という実験です。

結果は拍子抜けするほど余裕です。
なんと、足を着いた状態の”0”発進すらできました。(ハイモード)
暗峠の難所たるゆえんは、きつい斜度が休みなく続くため、一度足を着いてしまうと(斜度がキツすぎて)走り出すことができないということが挙げられます。
この場所では特に、どんな脚力のロード乗りでも厳しいはず。
結局、スタート地点からは20%消費して登りきることができました。

17%位の斜度を、ハイモードなら時速15km位で登ることもできました。だいぶバッテリーやチェーンに負荷がかかるので、そうそうはやりたくないですが平地のように進むことができるE-スポーツバイクに、正直ここまでとは思ってなくて驚きました。
ルイガノのASCENT e-sportsの場合
ASCENT e-sportsのスペック
タイヤサイズ:20×1.95
重量:18kg
変速:外装10段変速
バッテリー容量:36.0v×11.6Ah

本社より出発します。暗峠まではおよそ15km。
このモデルの特徴はミニベロであること。
車輪径が小さいと、街乗りのストップ&ゴーにおいては有利で、少ない力でこぎ出すことが可能です。
E-スポーツバイクだと、さらに軽いこぎ出しで、なおかつ平地であれば発進から7-10秒以内でアシストが切れる24kmに達するため、700cタイプと比べて電力消費を抑えることが可能です。
それは例えればハイブリッドカーでも同じことが言えます。
例えば、トヨタのプリウスは、発進の際はガソリンを使わず、なるべく電気の力を使うことで街中での燃費低減を実現しています。(当然空力とか他の要素も大きいですが)
事実、会社から暗峠までの区間(15km)はエコモードでバッテリー消費1%で済んでしまいました。発進を軽くさせることは、それだけメリットがあるのです。
E-スポーツバイクなのにアシストを使わない時間の方が長いというのはE-スポーツバイクに乗っている意味がないという人もいるかもしれませんが街乗りがメインで、発進を楽にしたい、途中にキツイ坂があるという使い方にはASCENT e-sportsはおすすめです。
E-スポーツバイクの中でも軽量で取り回しの良さも魅力です。
逆に、長距離を乗りたいという方は、700cタイプのE-スポーツバイクをおすすめします。

アシスト力という面では、正直ヤマハと大差はなく、どちらも拍子抜けする程楽に登れました。
「ハイ」モードならば、普段スポーツサイクルに乗らない女性でも登れてしまうのではないでしょうか。

急坂での”0”発信ももちろん問題なくできました。
例えば、夫婦やカップルでツーリングしている最中に越えなければいけない峠があったとして、男性が先に登ってしまい頂上で待ちぼうけ・・・女性は一人でつらい思いをして、頂上で不満を言われる・・・。体力差を埋めてくれるE-スポーツバイクは、そんな二人とも楽しくないツーリングの解決策になりそうですね。
ただ、E-スポーツバイは、初心者でももちろん楽しめるのですが、スポーツ車の変速の仕方は覚えておいた方がユニットやチェーン、ギヤへの負荷が少なく、故障の確率は減るでしょう。
坂で、例えアウター、トップ(一番ギア比が重い組み合わせ)で登ることができても、アシストなしの自転車に乗っている時と同じギヤ比で漕いだ方が長い距離を走れて、自転車にも優しいです。
YPJ-TC もそうですが、ASCENT e-sportsも手元でモードを簡単に変えることが可能です。
これにより、変速を変えるごとく、モードのチェンジを簡単にできます。

走行距離(DST)→積算距離(ODO)→走行可能距離(RANGE)→走行時間(TIME)→平均速度(AVG)→最高速度(MAX)の順番で切り替えられます。


なお、ASCENT e-sportsはライトが付属しないため、手元のライトはディスプレイのバックライトが点灯するのみです。
頂上までの消費電力は15%でした。モードを揃えたり、バッテリー容量が違うため、YPJ-TCとの消費電力の比較はできませんが、 ASCENT e-sportsの消費電力はかなり優秀です。
平地中心であれば、メーカースペックである115kmの倍以上は走れるのでしょう。
重要なことをサラッと書いてしまったのですが、E-スポーツバイクと、従来のシティサイクルをベースとした電動アシストの違いは、走行距離やスポーティな乗り味の他に、すごく重要な点があります。
それは、従来の電動アシスト自転車が、定められた1充電あたりの走行距離以上はほとんど場合走れないのに対して、E-スポーツバイクは負荷のかかる山岳地帯をずっと走り続ける場合を除いて、ほとんどの方がカタログ記載値以上の距離を走れるでしょう。
その理由として、従来のモデルはどんなに脚力がある人が乗っても、ダイレクトな推進力に変換されないため、アシストが切れる24km以上で走ることが難しいのに対して、E-スポーツバイクは、ダイレクトに推進力に変わる設計のため、速度が乗ってしまえばアシストが切れるスピード領域でもラクラク巡航できてしまうのです。
ということは、E-スポーツバイクは、1充電当たりの走行距離を必ずしも重視する必要はないのです。
メーカーカタログ記載値が100kmだから、100km以内の場所しか走れないではなく、ディスプレイを見ながらバッテリーマネジメントを行うことで、150kmでも200kmでもさらに可能性を広げることができるのです。
E-スポーツバイクは、普通の電動アシスト自転車とどれくらいアシスト力が違う?
私は、普段ブリヂストンのbikke(センターユニット、後輪駆動方式)に乗車しています。
それと比較したあくまで感覚値のパワー差ですが、YPJ-TCのエコモード(最弱)でbikkeのハイモード位という印象です。
当然重量やポジションも違うし、求められる性能も違うので、少々乱暴な比較ですが、それほどまでに体感上のアシスト力の違いを感じました。
電動アシスト自転車の限界
E-スポーツバイクは、正直未舗装路でなければ、登れない坂はないのではないかと感じます。
(暗峠を登れているのでないと思いますが)もし私の登りたい坂は上れるのか?と不安に思われた場合はぜひ登りたい坂の斜度を計測してみてください。専用の計測器がない場合はスマホのアプリでもたくさん出ています。
あくまで、私の体力を元にした個人的な結論ですが
一般的なシティサイクル型の電動アシスト自転車の限界は斜度15-17%まで。
E-スポーツバイクは40%程度までは登れるのではないでしょうか?
E-スポーツバイクはこれ以上もいけそうな気がしますが、問題は、登れる力はあるけど、空転せずグリップさせるなどの別のスキルが必要になりそうです。
参考資料 道路構造令第20条
参考資料
パーセントは水平100mに対して、垂直に何メートル上がるかで表し、1m上がれば1%となります。
※2
第20条
| 区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
| 第1種、第2種及び第3種 | 普通道路 | 120 | 2 | 5 |
| 100 | 3 | 6 | ||
| 80 | 4 | 7 | ||
| 60 | 5 | 8 | ||
| 50 | 6 | 9 | ||
| 40 | 7 | 10 | ||
| 30 | 8 | 11 | ||
| 20 | 9 | 12 | ||
| 小型道路 | 120 | 4 | 5 | |
| 100 | 6 | |||
| 80 | 7 | |||
| 60 | 8 | |||
| 50 | 9 | |||
| 40 | 10 | |||
| 30 | 11 | |||
| 20 | 12 | |||
| 第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
| 50 | 6 | 8 | ||
| 40 | 7 | 9 | ||
| 30 | 8 | 10 | ||
| 20 | 9 | 11 | ||
| 小型道路 | 60 | 8 | ||
| 50 | 9 | |||
| 40 | 10 | |||
| 30 | 11 | |||
| 20 | 12 | |||
道路構造令に規定する道路の最大縦断勾配を表1そして道路区分を
道路最大勾配は普通道路にあっては9% そして小型道路にあっ ては12%となっている。
道路の設計速度によっても変り、例えば、第3種小型道路で設計速度が60km/hの道路の最大勾配は8%。