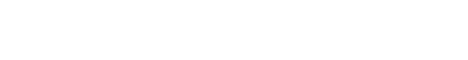TOPICS
- E-スポーツバイクとこれまでの電動アシスト自転車の違いって?
- 現在所有しているバイク(YPJ-ER)のスペックについて
- YPJ-ERを旅仕様にカスタム
- ぶっちゃけ使っててどうなのよ?ここがスゴイ!編
- ぶっちゃけ使っててどうなのよ?ここがオシイ!編
- まとめ
E-スポーツバイクとこれまでの電動アシスト自転車の違いって?
最近キャンパーなのかフィッシャーなのか分からなくなってきた富山山室店の清水です。
2018年6月にヤマハのYPJ-ERを購入してから、キャンプと釣りで激坂や悪路を走ってみたり、サークル活動でトレインしてみたりと色々試してきました。

今回は、実際にE-スポーツバイク(e-bike)を所有して見えてきた「ぶっちゃけ」を、できるだけ詳しく書いていこうと思います。
インプレに入る前にそもそも
『E-スポーツバイクとこれまでの電動アシスト自転車はどう違うんじゃ?』
と思いませんか?
私が調べ、考えたことを簡単に一言で書くと、
・軽快車(いわゆるママチャリ)に電動アシストドライブユニットを装着したものが電動アシスト自転車
・スポーツサイクルにドライブユニットを装着したものがEスポーツバイク
ということでした。
『え?じゃぁヤマハのPAS Brace(パス ブレイス)とかパナソニックのハリヤはどうなるのよ!』
というツッコミが聞こえてきそうですが落ち着いてください、、もう少し調べてみたところEスポーツバイクにはこんな特徴があることがわかりました。
①バッテリーがダウンチューブに装着 or 一体となっている(一部例外もある)
②車体だけでなくアシストユニットもスポーツ自転車用に開発された軽量で小型なものが装備されている
③ドライブユニットの稼働方式が違う(主流はギアクランク中心部のボトムブラケット周りに装着するミッドマウント式)
これまでの電動アシスト自転車はボトムブラケット軸より後ろにアシスト機構を持つ二軸式が主流で、ボトムブラケット軸とは別にアシスト力を伝える歯車があるのが一般的でした。
また、これによりバッテリー積載スペースが必要となることでホイールベースが伸びる傾向にありました。
先に挙げたPAS Brace(パスブレイス)やハリヤも、同様の仕様が施されており、アシストユニットにはシティサイクルタイプのものが搭載されていました。
一方、E-スポーツバイクは、上記③のミッドマウント式で言えばボトムブラケット軸を直接アシストする方式のため、余計な抵抗がなくペダルを踏んだ力にアシストを上乗せできるようになっています。
バッテリーをフレームに搭載することでボトムブラケット軸とリアホイール軸の間隔が近くなり、ペダリングに対する反応や曲がる際のクイックさが増し、よりスポーティーな走りが実現したのです。
と、あくまで私が調べた限りの情報と見解です。
現在所有しているバイク(YPJ-ER)のスペックについて
難しい話はここら辺にして、所有しているYPJ-ERの簡単な仕様をご説明します。

YPJ-ER (Lサイズ)
フレーム・フォーク:アルミ
FD:SHIMANO Tiagra 2s 50T/34T
RD:SHIMANO Tiagra 10s 11~32T
ブレーキ前後:SHIMANO Tiagra 油圧式ディスクブレーキ
タイヤサイズ: 700×35C
車両重量: 19.8kg
一充電走行距離:ハイモード 93km
スタンダードモード 111km
エコモード 152km
プラスエコモード 242km
これに下記のバイクパックを装着
ジャイアント:SHADOW ST TT PANNIER BAG(※ネット通販での取り扱いなし)
ブラックバーン:OUTPOST FRAME BAG (SMALL)
トピーク:BackLoader (15リットル)
YPJ-ERを旅仕様にカスタム
普段はレインウェアとお菓子ぐらいしか入れてないですが、キャンプや釣りに行くときは道具一式おおよそ3~5kgプラスです。

ちなみに現在は少しいじってこんな感じの仕様です

変更した箇所
タイヤ: WTB Cross Boss Tan Wall 700×35c(※ネット通販での取り扱いなし)
バーテープ:Deda ミストラル
サドル:あさひ スタンダードサドル(BR)
ペダル:あさひ アルミフラットペダル(SL)
スタンド:純正スタンド
Fフォークキャリア:ボトルケージアタッチメント+ブラックバーン アウトポストカーゴケージ
※スプロケットやギア、ホイール径、タイヤの太さ変更など、アシストユニットのアシスト比に関わる部品の改造は禁止とされています。
ぶっちゃけ使っててどうなのよ?ここがスゴイ!編
私のYPJ-ERの使用用途としては以下の通り
使用用途
キャンプ、渓流釣り、サイクリング
平地:60% 坂道(山道)・グラベル:40%
現在までの総走行距離:1090km

E-スポーツバイク×バイクパッキングがやりたくて購入したので当然ではありますが、キャンプや釣りばかりに使っていました。

耐久テストもしたかったので、結構激しい目のグラベルや悪路を見つけては問答無用で突っ込んでいたので、かなりハードな使い方をしています。
さて本題の
『ぶっちゃけ使っててどうなのよ?』
の話に移ります。
E-スポーツバイクのココがいいね!
①坂道軽い・発進早い・向かい風こわくない
「電動なんだからそりゃそうでしょ!」なんですけれども、想像以上でした。
先にも書いた通り、アシストユニットが軽量で小型なことと、ミッドマウント式のメリットが加わり、恐ろしい程の加速力です。(いい意味で)
24kmまで2~3秒で加速しますが、車体重量20kg+バイクパッキング5kgでも減速しらずです。
また坂道走行もピカイチでキャンプ場手前は10%以上の坂なんてザラですが、上記条件で登っても全く重くないです。
ただし、坂道に関してはスタンダードモードだと少し重く感じます。ハイモードにして時速15~20kmで世間話しながらでも上れます!
ちなみに、アシストが強すぎて心拍数がほとんど上がらないため、晩秋のような寒い時期には中々体が温まらずわざとアシストOFFにして走っていました。
②グラベルに強い
山中でお化けが出そうなグラベルに突っ込み、デカい石がゴロゴロしている所や、雨でぬかるんだ道も難なくクリアできました。
ハンドルが取られてしまいそうな場面でも、アシストが推進力となりふらつくことはありませんでした。
(ただし、調子に乗ってスピードを出し過ぎると崖に真っ逆さまなので気を付けましょう。)
③バッテリーの持ちが良い
これは本当に良い意味で裏切られました。
本車体のアシストでの走行距離ですが、道路状況にもよりますがカタログ値より約1.8~2倍多く走れます。
スタンダードモードではカタログ値111kmなので、つまり200km近く走れる計算になります。
これはヤマハHPの「YPJ走行距離チャレンジ」でも証明されていて、あくまで推測ですが25~30kmのアシストOFFの領域で走っている時間が長いからだと思われます。
ちなみに激坂で常にアシストが効いた状態や24km以下でゆっくり走行した場合はカタログ値通りでした。
④アシスト切れても意外に軽い
24kmまで加速してそれ以上はアシストOFFになるわけですが、アシストがいつ切れたかわからないぐらい切れたあとも軽いです。
購入する前はシティタイプの電動のように電源が切れると激重になると思っていましたが違いました。
晩秋の発汗チャレンジしているときの発進は若干の重さは感じますが、その後のスピードに乗った状態は非常に快適です。
ロードバイクに混じっての30km巡航トレインでも問題なくついて行けました!
⑤防水性が高い
アシストユニットやバッテリー周辺の防水性能の話ですが、新YPJシリーズはどんなに水を被せても故障しないとメーカー様が仰っていました…。
購入検討中に、「結構ハードな使い方するんですけど」と伝えたところ、「大丈夫!壊せるものなら壊してみてください!」バリに言っていたので本当に壊す勢いでやってみようと、一時間50mmを超える滝のような雨に一日中打たれて走りましたが大丈夫でした!
※ただし当然バッテリーを外して水に沈めるのはやめてほしいとのことです。
⑥ライトが明るい
カタログ値に記載がないためこれぐらい!というのは表現しにくいですが、とにかく明るいです!(体感的にはMOONメトロシリーズやVOLT400よりは明るいです)
またバッテリー供給式のため電池を食ってしまわないか心配でしたが、現時点でライトを使ったから走行距離が減るという感覚はありません。
⑦純正のスタンドが良い
そこ?と思うかもしれませんが、かなり大事です。
頑丈なスタンドが見事に車体を支えてくれてピクリともしません。
このことで駐輪する際の転倒などの心配が一切なくなり安心感が増しました。
YPJシリーズご購入のお客様は、同時にお求めいただくことを強くおすすめします。
⑧USBポートの給電機能が良い
新YPJのファンクションメーターにはUSBポートが搭載されています。
これによりスマートフォン等への給電が可能なのですが、キャンプ等ではこれが重要となります。
少しでも荷物を減らしたいバイクパッキングの旅ではモバイルバッテリーのスペースすら減らしたいのが正直なところです。
この給電機能により、スペースを減らせたことだけでなくスマートフォンやバッテリー式ランタンの充電切れが恐くなくなりました。
もちろん②のバッテリーの持ちも相まって電池消費を気にする必要はありません。
ぶっちゃけ使っててどうなのよ?ここがオシイ!編
いいところもあれば、続いて、ちょっと気になるところ
Eスポーツバイクのココがオシイ!
①車体が重い
20kg近い車体は、走行中の重さはさほど感じないものの押して歩くときは結構な重さです。
特に、少しの段差を持ちあげる時や、車への車載時、そしてバイクスタンドに掛けるだけでも「ふんぬぁらばぁ!!」と気合を入れて(入れなくてもいいですが)持ち上げています。
②値段が高い
これは今のEスポーツバイクの課題の一つのような気がします。
YPJ-ERは一台で30万を超えるような値段です。
もう少し普及すれば価格は安くなるのかもしれませんが、現時点では覚悟がいる価格、というのも確かです。
③モーター音が気になる(かもしれない)
結論から言うと私は気になりません!
気になる人には気になるというレベルです。
どんな音かお伝えするのは難しいですが、激坂の抜き去りの際に「後ろからプリウスが来たかと思った」と言われたことがあります。
④高速巡航には向かない
先ほど書いた通り、30kmの巡航には問題なくついて行けるかと思います。
しかし、それ以上の巡航に関してはエンジン(乗る人)次第です。
私の場合は30km以上の巡航が始まったら「皆さんどうぞ楽しんできてください」という気持ちでフェードアウトします。
それ以外にも、25~30kmでのゆるい上り坂はスピードが乗らない気がします。
余談ですがカスタム後の現行仕様では30kmトレインについて行けなくなりました(笑)
⑤輪行不可能(な気がする)
これはですねぇ、やってないのでわかりません!
と言うよりやりたくないです(笑)
⑥アシストスイッチが変更しづらい
アシスト変更スイッチがステム左側に装備されていますが、ブラケットから一度手を離して操作しなくてはならず扱いづらく感じます。
特に、「プラスエコで走行していて曲がったら急に坂道」のようなプラスエコ→ハイモードへの切り替え、「坂道を上りきったあとにアシストOFFにしたい」ときのハイモード→OFFのようなケースは高速連打で変更しなくてはなりません。
まとめ
今回はほとんどバイクパッキングでの使用のため、偏った評価となりましたが少しでもご参考になれば幸いです。
半年使っていま言えることは、「キャンプや釣り、その他Eスポーツバイクを通して何かアウトドアをやってみたい」という使い方は
間違いなく『買い』です。
間違いありません。
上記での使用に関しては、大げさではなく良い意味で『劇的に変わりました』
例えばノンアシストでやっていたキャンプでは、なんだかんだで積載した荷物が重く、坂道でゼーゼー登った後に設営して食事の準備をしてと、その工程だけで疲れ果ててしまっていました。(楽しいですけどね)
E-スポーツバイクに乗り換えてからは、現地に着いてから余力があるため、例えば一度山を下りて買い出しに行くことが苦でなくなったり、時間があれば現地周辺の観光に行ってみたり、あえて山のてっぺんを目指してみたりと、その旅の幅が広がり新たな思い出作りに一役買いました。
川で行う「渓流釣り」については、川に近付く⇔道路に戻る を繰り返すため、坂道走行を筋トレのごとく繰り返します。
この筋トレが無くなっただけでも釣りに集中できるってものです。それは釣果にも影響するのではないでしょうか。(…私は釣れていませんが。。)
ストップ&ゴーの多い街中でも恩恵を受けられますが、是非、購入された方には街中でとどまらず、今まで自転車で行けなかったところ、行きたかったところに足を運んでほしいです。
総評
E-スポーツバイクは、「坂道を見つけるとあえて行きたくなってしまう」そんなバイクです!!
先ほど費用面での問題を挙げましたが、ここまでの費用対効果が得られるのであれば私ならもっと高くても買います!
払ったコスト以上に「達成感・充実感」を得られる新世代スポーツバイクです

TEXT:富山山室店 Shimizu