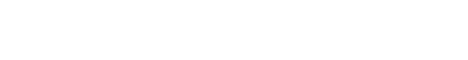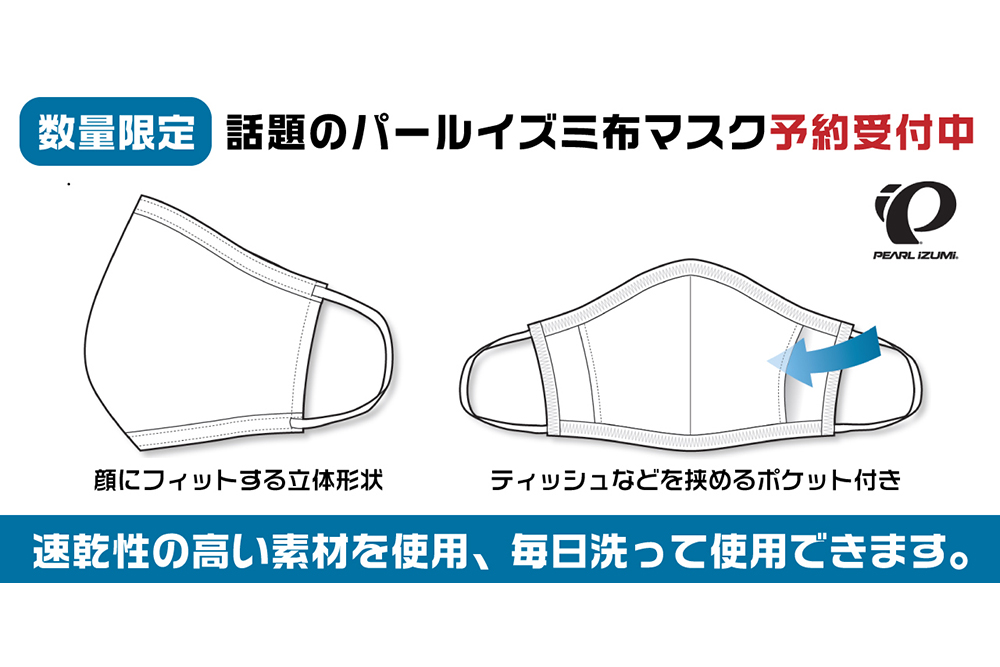シートポストの交換って??どんなタイプを選べばいいの??
最近、本格的に自転車に乗り始めたばかりのスタッフから質問がありました。
「シートポストを交換したいんだけど、様々な種類の商品があって、何をどう選べばいいの?」
このメルマガを読んでいただいている方の中にも同じような疑問をお持ちではないかと思い、今回は簡単にシートポストの種類に関して書いてみます。
まず、大前提として今回の記事はフレームに対して専用品として準備されているシートポストではありません。
最近では各自転車ブランドでフレームに対して専用品のシートポストを出されているメーカー様も多いです。
そういった場合はメーカーオプションとして種類やオフセットなどが違うシートポストが用意されている場合もあるので、各メーカーのHPなどをご確認ください。
⇒ポイントその①【シートポストのサイズ】
まずは、お持ちの自転車のシートポストのサイズを確認しましょう!重要なのはシートポストの“径”と“長さ”!
シートポストの径を確認するときは、一度シートポストをフレームから抜いてみます。フレーム内に収まって部分にシートポストの直径が刻印されていることが多いです。
代表的なサイズには27.2mm、31.6mm、34.9mm…など、各メーカー、フレームの素材などによって様々です。
「0.2mmぐらいの差だったら大丈夫だろう!?」いえ、ダメです。サイズはメーカーが指定するサイズのものをご使用ください。そうしなければフレームに対して確実な固定ができず、走行中にサドルが下がってきたり、回ってしまうことがあり危険です。
フレームメーカー様によっては、ホームページやカタログなどに使用されているシートポスト径が記載されている場合もあります。
もし、どうしてもシートポストの径が分からなければ、「ノギス」と言う計測器がありますので、ノギスを使って計測することもできます。
シートポストの長さに関しても、現在使用しているシートポストを同じ長さを選ぶのが基本。極端に長すぎたり短すぎるものはダメです。
シートポストは一定量、フレームの内部に入っていないとフレームやシートポストの破損(破断)に繋がる可能性があります。短すぎるシートポストを使って、これまで変わらないサドルの高さで使用するとフレーム内部に十分な量のシートポストが挿入されていない場合がありますからね。
⇒ポイントその②【シートポストのオフセット】
オフセットとは“ヤグラ”と呼ばれるシートポスト上部のサドルを固定する部分が、シートポストの真上にあるのか?それとも少し後ろにズレた位置にあるのか?と言うこと。
シートポストの真上にヤグラがある場合はオフセットが「ゼロ」と言うことなります。
シートポストのオフセットを変えることでサドルの前後位置が変更されるため、自転車に乗った時のポジションが変わります。今乗っている自転車が少し窮屈に感じる場合は後方にオフセットされたシートポストに変更することで、サドルの座る位置が後ろに下がってポジションが変わることで今まで以上に力を出せるようになったり長距離のサイクリングが楽になる場合もあります。
0mmオフセットの代表的なシートポスト

25mmオフセットの代表的なシートポスト

1本のシートポストで0mm/25mm両方のオフセットに対応したシートポスト

⇒ポイントその③【サドルの固定方法・ヤグラの形状】
こちらに関してはそれほどシートポストの交換に重要ではないかもしれませんが、参考までにご確認いただければ幸いです。
サドルを固定している部分、通称“ヤグラ”と言う部分の固定方法にも様々なタイプがあり、サドルの角度調整がより細かく行えたりします。
1本のボルトで固定するタイプ
角度調整時やサドルの交換時に回さなくてはいけないボルトが1本なので素早く比較的簡単に作業が行えます。

前後2本のボルトで固定するタイプ
前後のボルトを締めたり緩めたりすることで、より微妙な角度調整が可能です。

左右からボルト1本で固定するタイプ
固定するためのボルトも1本で作業性が良く、サドルの角度調整幅も他のものに比べて非常に広い角度で行えます。

上記で説明した以外にも、カーボンタイプのレールを使ったサドルだったり、特殊な形状のレールなど、サドルの種類によっても選ぶべきシートポストも変わってくる恐れもありますので、分からない場合は、最寄りのサイクルベースあさひにご相談ください。
今回は、基本的なシートポストの選び方をご説明させていただきました。
TEXT:kisshie
自転車の汚れ防止に必須のカバー
自転車は屋外に駐輪しているという皆さん、汚れや劣化が気になりませんか?
雨で濡れるとサビの原因になりますし、乗る頻度によっては、ホコリが積もったりもします。
紫外線によるダメージでサドルやグリップが劣化することもあります。
いつまでもキレイなままで、長く使いたいという方には自転車カバーがオススメです。
さらに、カバーで自転車を隠せば、盗難やいたずら被害を未然に防げるという効果もあります。
全体をすっぽり覆って、雨風から自転車を守るタイプが使いやすく効果も高いです。
まずはカバーをかけたい自転車の全長(前カゴの端から後輪までなど)を測って
丁度いいサイズのカバーを選ぶことが重要です。
自転車の種類によって形は様々なので、実際の全長・ハンドル高・ハンドル幅を測って、
カバーのサイズと比較することをおすすめします。

破れにくい厚手の生地を使用していて、裾が絞れるようになっているので
強風でカバー飛ばされたりすることを防止します。こちらは原付きバイクにも利用可能です。

カバーをしたままバッテリーの着脱ができるようにファスナーが付いているので電動自転車にオススメです。
さらにカバーをつけたままでワイヤー錠で施錠できる前後ホール付き。
風飛び防止バックル、コードロック付き裾絞り紐を装備。
バタつきを防止して車体にぴったりフィットします。
「子ども乗せハイバック」付き自転車はこちらを選んでください

また、電動自転車は専用のカバーがあものもあります。
その他にもスポーツタイプ向けや、キッズ用など様々な自転車カバーをご用意していますので、ぜひご検討ください。
TEXT:sorajirou